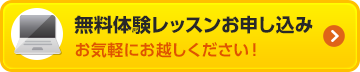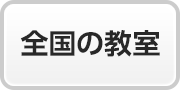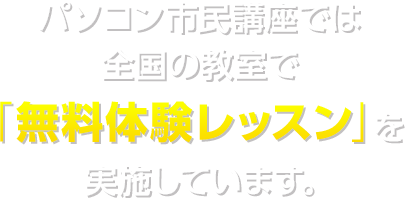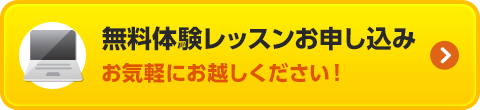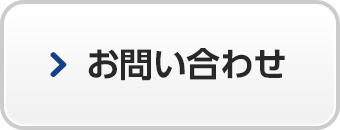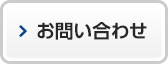共通テスト「情報Ⅰ」対策|問題の傾向、勉強法とスケジュール
カテゴリー:リスキリング・DX
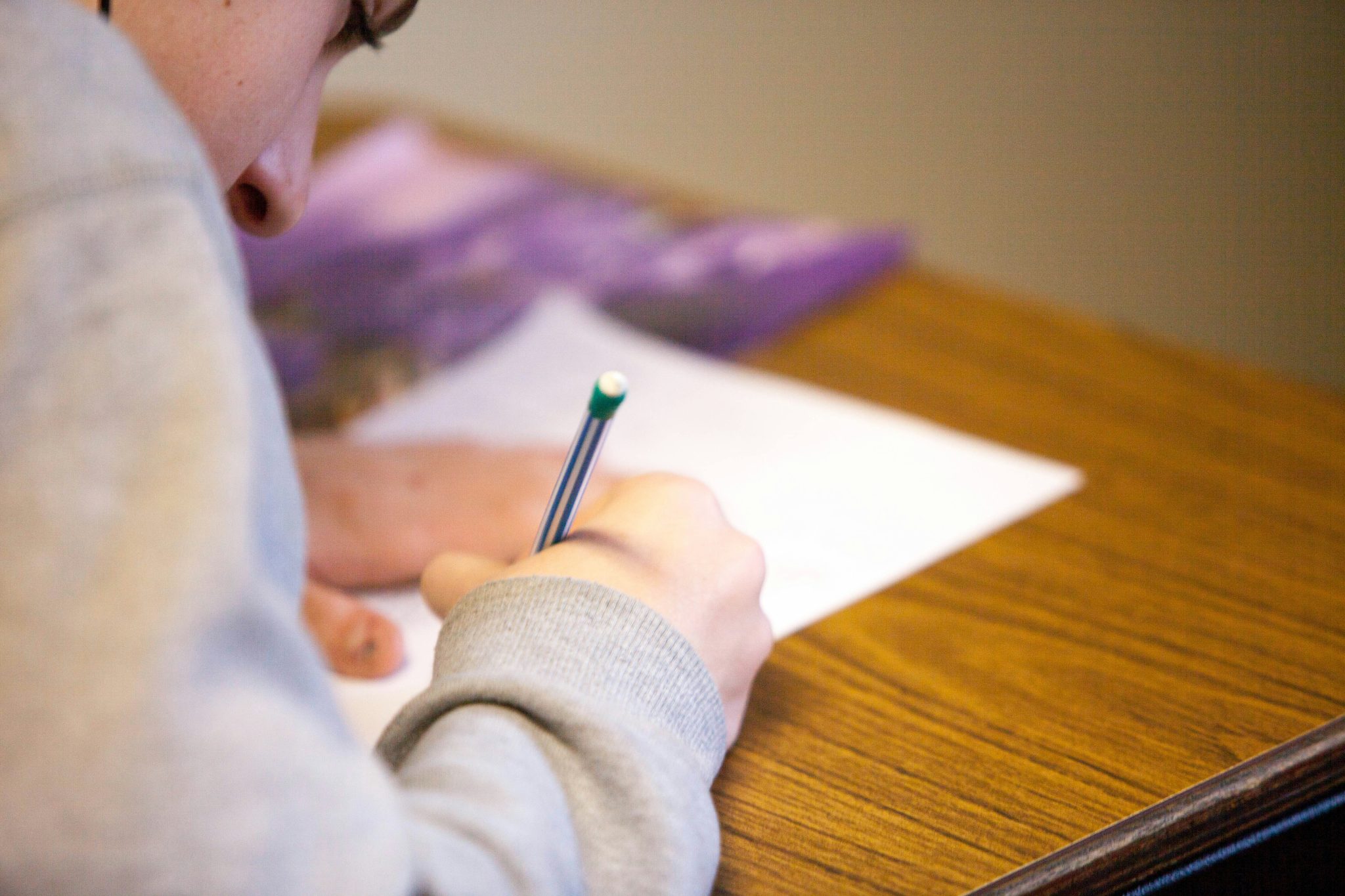
共通テストの「情報」は初めての試験科目であり、どのように対策すればよいか悩む人も多いでしょう。限られた時間で効率よく学ぶには、重要なポイントと対策を押さえた学習が必要です。本記事では、共通テスト「情報」の効率的な勉強法とスケジュールを解説します。
目次
共通テスト「情報Ⅰ」とは何か
共通テスト「情報Ⅰ」は、高校生が情報技術の基礎を理解し、活用する能力を評価する試験です。情報の収集・分析・整理・発信プロセスを学び、問題解決に応用する力を養うための試験です。
単なる技術教育に留まらず、情報が社会や個人に与える影響の理解を深め、未来の情報社会で活躍するための基盤を築くことを目的としています。
共通テスト「情報Ⅰ」の導入時期と背景
「情報Ⅰ」は、情報社会の進展を背景に、2025年度から大学入学共通テストに導入されました。この新しい科目の導入は、情報社会の進展に伴い、高校生の情報に関する基礎的な理解と実践的スキルの習得が必要とされていることが背景にあります。導入に際して、従来の教育課程からは大きな変更が見られ、学生が社会で直面する課題に主体的かつ適切に対応する能力や、思考力・判断力・表現力を育むことが期待されます。
共通テスト「情報Ⅰ」は受験必須か
受験必須であるかどうかは、受験生が志望する大学や学部によって異なります。多くの大学が入試科目として「情報Ⅰ」を設定しているものの、必須科目としている大学もあれば、選択科目としている大学もあります。情報社会が進展する中で、情報リテラシーの重要性が増していることから、「情報Ⅰ」を受験することが推奨されるケースが増加しています。
また、文系であっても情報活用能力が求められる場面が増えているため、受験生にとって「情報Ⅰ」は重要な選択肢となります。したがって、受験生は志望校の入試要項をしっかりと確認し、「情報Ⅰ」が自分の受験プランにどのように関わるのかを理解することが重要です。さらに、大学のカリキュラムや卒業後のキャリアを考慮して、情報科目の受験が自分にとってどのような意味を持つのかを考えることも有益です。
情報技術の基礎を学ぶこの科目は、単なる受験対策にとどまらず、将来的なスキルの向上にもつながる可能性があります。そのため、受験必須かどうかにかかわらず、積極的に学ぶ姿勢が求められます。
共通テスト「情報Ⅰ」の出題内容と配点
共通テスト「情報Ⅰ」の出題内容は、情報倫理や情報セキュリティに関する理解が重視され、大問4つで構成「情報社会の問題解決・コミュニケーションと情報デザイン・コンピュータとプログラミング・情報通信ネットワークとデータの活用」が含まれます。
また、情報の可視化やデジタルデータの正確な解釈を求める問題も出題される傾向もあり、受験者の論理的思考力や問題解決能力を評価します。
本章では、4つで構成の詳細内容と配点について解説します。
共通テスト「情報Ⅰ」の出題内容
共通テスト「情報Ⅰ」は、学習指導要領の4つの領域に対応した大問4つで構成されています。試作問題の傾向に基づくと、以下のすべての分野からバランスよく出題されます。
情報社会の問題解決
情報技術が社会に与える影響、情報倫理、知的財産権、情報セキュリティなどの基礎知識が問われます。
コミュニケーションと情報デザイン
メディアの特性や、情報を効果的に伝えるためのデザイン(UI/UX)、アクセシビリティ、さらに二次元コードの仕組みなどが含まれます。
コンピュータとプログラミング
アルゴリズムの理解や、独自のプログラミング用共通言語(DNCL)を用いたコードの読み取り・修正能力が試されます。
情報通信ネットワークとデータの活用
プロトコルやIPアドレスなどのネットワークの仕組みと、統計的な手法を用いたデータ分析・解釈の能力が評価されます。
共通テスト「情報Ⅰ」の配点
配点は通常、100点満点で構成されており、問題の難易度に応じて各設問に配分されます。選択問題が多く、短い文章や図表を用いた問題も含まれるため、理解力とスピーディな判断力が要求されます。
例えば、プログラミングの基礎を問う問題では、簡単なコードの修正やその出力結果を予測する能力が試されます。また、情報倫理やセキュリティに関する問題では、法律やガイドラインについての知識が必要です。これらの内容は、情報技術が日常生活や社会にどのように影響を及ぼしているかを理解するための重要な要素となっています。
問題のバリエーションは多岐にわたり、受験生の総合的な情報処理能力を測ることを意図しています。そのため、単に知識を詰め込むだけでなく、実際の問題に
共通テスト「情報Ⅰ」の試験に向けての対策方法とアドバイス
共通テスト「情報Ⅰ」は、プログラミングやデータ分析など、これまでの教科とは異なるアプローチが求められる科目です。高得点を目指すためには、単なる暗記に頼るのではなく、出題の全体像を把握した上で、計画的に学習を進める必要があります。
ここでは、効率的にスコアを伸ばすための具体的な対策方法と、試験に向けた学習アドバイスを解説します。
学習期間を把握し勉強スケジュールを立てる
共通テスト「情報Ⅰ」の勉強スケジュールを立てる際には、まず全体の学習期間を把握することが重要です。受験までの期間を逆算し、各段階で達成すべき目標を設定しましょう。具体的には、基礎知識の習得、過去問演習、模擬試験の実施の三段階に分けると効果的です。
勉強スケジュール例
- 基礎知識習得期間(約2〜3ヶ月):教科書や参考書を使って情報Ⅰの基本概念を理解することに専念します。毎日少しずつ進めることで無理なく知識を蓄積します。
- 過去問演習の期間(約3ヶ月):過去の出題傾向を分析しながら問題を解くことで、実際の試験形式に慣れていきます。間違えた問題を復習し、理解を深めることが重要です。
- 模擬試験実践練習期間(2回以上):本番を意識した時間管理と精神的な準備を行います。模擬試験は少なくとも2回は実施し、結果を分析して弱点を補強します。
試験出題範囲の理解
共通テスト「情報Ⅰ」の対策方法を効果的に行うためには、まず試験の出題範囲をしっかりと理解することが重要です。情報Ⅰの試験では、情報の科学的な理解や情報技術の活用方法が問われます。そのため、基本的な情報技術の知識を確実に身につけることが必要です。具体的には、プログラミングの基礎、データベースの基本概念、アルゴリズムの理解、ネットワークの構造といった内容に慣れておくと良いでしょう。
過去の試験問題や模擬試験を実施
過去の試験問題や模擬試験を活用して、問題の形式に慣れることも大切です。問題演習を通じて、時間配分や問題の傾向を把握し、実際の試験でどのように対処するかをシミュレーションしておくと安心です。特に、情報Ⅰでは思考力や問題解決能力が求められるため、単に知識を暗記するだけでなく、実際に手を動かして問題を解くトレーニングを積み重ねることが効果的です。
日常生活で情報技術を意識する
日常生活での情報技術の応用例を意識的に観察し、実際の問題と関連付けて考える習慣をつけると、試験の応用問題にも対応しやすくなります。関連するニュースやトピックに触れることで、情報分野の最新動向にも精通しておくと、より深い理解が得られます。
最終確認ポイントと試験直前施策
共通テスト「情報Ⅰ」の最終確認として、頻出の基本用語やアルゴリズム、ネットワークの知識を総復習しましょう。過去問や模試で時間配分に慣れ、特に計算やプログラム問題は効率的に解く練習が不可欠です。当日に備え、持ち物や会場へのアクセスは前日までに確認を。また、十分な睡眠と栄養で体調を整え、リラックスして試験に臨むことも大切です。これらの準備を万全にして、実力を発揮してください。
共通テスト「情報Ⅰ」を受験するメリット
共通テスト「情報Ⅰ」で問われるデータ分析や情報倫理、ネットワークの知識は、大学での学びに留まらず、将来の職業や日常生活でも役立つ非常に有用なスキルです。
さらに、「情報Ⅰ」を選択することには、以下のような大きなメリットがあります。
- 他の受験生との差別化:情報技術の知識は、現代のさまざまな分野で高く評価されます。将来、社会に出たときに大きなアドバンテージとなり、他の受験生と差をつける強力な武器になります。
- 他教科への好影響:試験勉強を通じて培われる論理的思考やデータ分析のスキルは、数学や理科など、他の科目の問題解決能力を高め、総合的な学力向上にも貢献します。
- 情報技術に関する最新の動向を意識できるようになる:急速に進化する技術環境への関心が高まり、社会で必須となる柔軟性や適応力を養うきっかけになります。
このように、「情報Ⅰ」の受験は単なる試験対策に留まらず、ご自身の未来のキャリア形成においても大きな意味を持つ選択と言えるでしょう。
共通テスト「情報Ⅰ」を受験する際の注意点とNGな対策
共通テスト「情報Ⅰ」を受験する際には、いくつかの注意点と避けるべきNG行動が存在します。
気をつけるべきポイントを抑え、NG行動を避けることで、共通テスト「情報Ⅰ」において良い結果を得られるでしょう。これらの注意事項を念頭に置き、万全の準備を整えて試験に臨むことが成功への道です。
注意点!試験の公式ガイドラインをしっかりと確認する
まず、試験の公式ガイドラインをしっかりと確認することが重要です。出題形式や配点比率に関して誤った認識を持っていると、効率的な対策ができません。また、時間配分のミスも大きな落とし穴です。試験時間は限られているため、事前に模擬試験を通じて時間配分を練習し、一問に時間をかけすぎないように心がけましょう。
さらに、答えを記入する際には、問題用紙の指定に従って正確に記入することが求められます。誤った欄に記入すると、せっかくの正答が無効になってしまう可能性があります。特に、マークシート形式の場合、ダブルチェックを行い、記入ミスを防ぐことが大切です。
NG対策!知識を丸暗記
情報Ⅰの試験においては、過去問や類似問題を解くだけではなく、情報の基本概念や用語の理解を深めることにも力を入れましょう。ただ単に知識を丸暗記するのではなく、実際の問題に応用できるように理解を深める学習が求められます。
役立つ教材とリソース
まず、基本的な知識を固めるためには、学校で使用されている教科書や、情報科目に特化した参考書を活用することをお勧めします。これにより、試験範囲の基礎をしっかりとカバーできます。
次に、問題集は実践力を養うための重要なリソースです。過去問や類似問題を収録した問題集を使って、出題傾向を把握し、時間管理や解答テクニックを身につけましょう。また、解説が詳しく書かれているものを選ぶことで、間違った問題の理解を深められます。
オンラインリソースも非常に有用です。教育系のYouTubeチャンネルや、情報科学に特化したウェブサイトは、視覚的かつインタラクティブな学習を提供してくれます。特に、動画コンテンツは難解な概念を分かりやすく説明してくれるため、苦手分野の克服に役立つでしょう。
さらに、情報科目に関連するオンラインフォーラムやSNSグループに参加することもおすすめです。これらのプラットフォームを通じて、他の受験生や専門家と交流し、最新情報や勉強法を共有できます。
最後に、模擬試験を活用して、実際の試験環境をシミュレートすることも重要です。これにより、試験本番の緊張感を体験し、自分の弱点を明確にすることができます。模擬試験のスコアを分析し、学習の改善点を見つけることで、効率的な勉強を進められるでしょう。これらの教材とリソースを組み合わせて、総合的な学習計画を立てることが、共通テスト「情報Ⅰ」で高得点を目指すための鍵となります。

この記事を書いた人:パソコン市民講座編集部
リクルート、出版社、テレビ通販、ECなど複数業界で「伝える」「売る」「育てる」の現場を横断してきた実践派マーケター。現在は教育系企業でビジネスDX・SNSマーケ・EC講座などを設計し、受講からキャリア支援まで一気通貫で支援する構造設計を担う。 コンテンツ制作から広告運用、LP・CRM設計、SNS戦略、MA活用、商品開発、社外提携まで、ひとつの講座を“仕組みごと”作るプロフェッショナル。