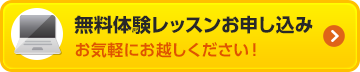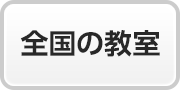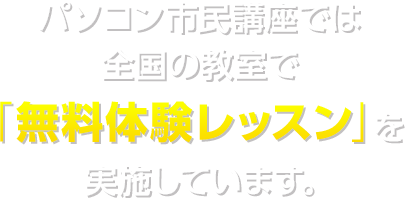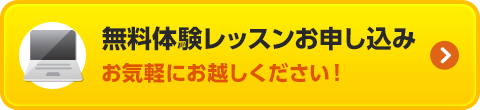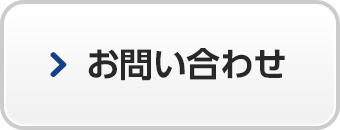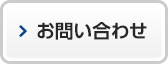社会人の学び直しとは?リカレント教育の意味・始め方・支援制度を徹底解説
カテゴリー:キャリアアップ・転職
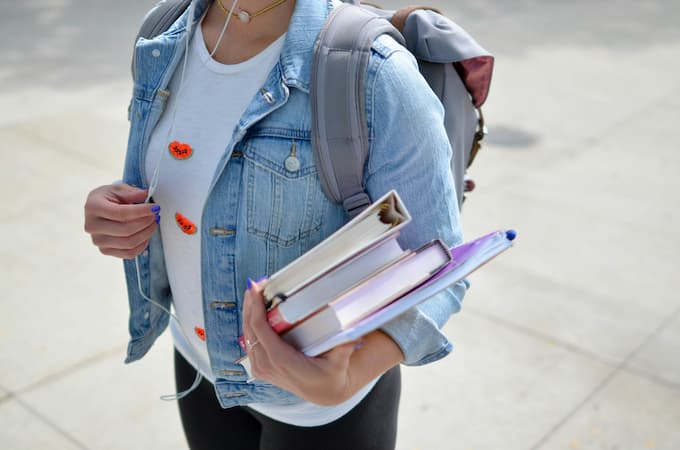
仕事を続けながら、新しいスキルを身につけたい」「キャリアに行き詰まりを感じている」そんな社会人の方が今、急増しています。忙しい日々の中で「もう一度学び直したい」と思っても、時間や費用のハードルが高く、なかなか行動に移せないものですよね。
しかし近年、国や企業が推進する「リカレント教育(学び直し)」制度の充実により、社会人でも学びやすい環境が整っています。オンライン講座や大学・専門学校での学び、給付金や奨学金など費用面の支援も充実し、選択肢はこれまでになく多様です。
本記事では、「社会人の学び直し」をテーマに、リカレント教育の意味から実践方法・支援制度までをわかりやすく解説。あなたのキャリアを再構築するための具体的なステップを紹介します。
社会人の学び直しは、キャリアの可能性を広げるチャンスです。今日から、あなたの“第2の学び”を始めましょう。
目次
リカレント教育とは?―社会人の「学び直し」を支える考え方
リカレント教育とは、社会人が教育機関などで新たな知識や技能を学び直すことを指します。 急速に変化する社会や労働市場に対応するために、社会に出た後も自分に必要なスキルや技術を学び続けることを目的とした教育の仕組みです。
現代では、IT技術の進化やグローバル化により、必要なスキルが常に変化しています。こうした環境下で「社会人の学び直し」は、キャリアを維持・向上させるための重要な手段となっています。
文部科学省や厚生労働省もこのリカレント教育を積極的に推進しており、資格取得・スキルアップを支援する制度を多数整備しています。
リカレント教育の特徴
- 社会人が自分のペースで学べる柔軟な学習形態
- 仕事と両立しやすい時間・場所の選択肢
- 実務に直結した内容が多く、すぐに活かせる
- 会社の成長や自身の昇進・転職など、キャリアの再構築を目指せる
リカレント教育は、単なる知識の習得ではなく、「キャリアを再設計する学び」として注目されています。
リカレント教育の目的
社会人の学び直しは、単なる再学習ではなく「人生100年時代のキャリア戦略」です。 特に現代では、一度得たスキルで一生働ける時代ではなくなり、生涯を通じた継続学習が不可欠になっています。
リカレント教育の主な目的
- 変化する労働市場・技術革新への対応力を高める
- スキルアップ・キャリア形成を支援し就業機会を広げる
- 学び直しを通じて自己実現・豊かな人生を実現する
- 国の人材育成政策の一環として社会全体の競争力を高める
学び直しは、社会人が自らの可能性を再発見し、変化に強い人材へと成長するための第一歩です。
生涯学習との違い
リカレント教育と生涯学習は共に社会人の学びを支える重要な概念ですが、その目的とアプローチには微妙な違いがあります。生涯学習は、人生を通じて継続的に学び続けることを重視し、個々の興味や趣味、自己啓発といった幅広い分野を対象としています。これは、知識の幅を広げたり、趣味を深めたりすることを目的とし、学びが必ずしも職業に直結するわけではありません。
一方、リカレント教育は特に職業能力の向上やキャリアチェンジを目指す社会人の「学び直し」を支援することに重点を置いています。リカレント教育は、職業に関連する専門知識や技術を習得し、社会人としてのスキルアップやキャリアアップを目的としています。
社会人がリカレント教育を受けるメリット
社会人にとっての学び直しには、多くのメリットがあります。
- キャリアアップの可能性が広がる
資格やスキルの習得により、転職・昇進のチャンスが増えます。 - 仕事の効率化
最新のITスキルや知識を取り入れることで業務改善につながります。 - 自己成長とモチベーション向上
学ぶことで自信が生まれ、仕事への意欲も高まります。 - 社会的信用の向上
資格・専門知識の取得は社内外での評価アップにも直結します。
変化の激しい社会を生き抜くために、リカレント教育は「社会人の武器」となるでしょう。しかし、忙しい社会人は時間の制約や仕事や家庭との両立を迫られるのも事実です。次項では、社会人の学び直し方法について解説します。
社会人のための具体的な学び直し方法

社会人が学び直しを始める際は、「目的に合った学び方」を選ぶことが大切です。 ここでは代表的な学び方を紹介します。
オンライン講座の活用法
オンライン講座は、時間・場所を選ばず学べる現代的な学び方。 パソコンやスマホで受講でき、スキマ時間の活用にも最適です。
メリット
- いつでもどこでも学べる柔軟性
- 費用が安く、無料講座も豊富
- 録画視聴で繰り返し学習が可能
- 資格対策・ITスキル・ビジネススキルなど多分野を網羅
活用のコツ
- 目的を明確にして講座を選ぶ
- 無理のないスケジュールを立てる
- 質問・サポート体制のある講座を選ぶ
- 口コミやレビューをチェック
文部科学省による講座や、YouTubeなどの民間プラットフォームも有効活用できます。 オンライン学習は最も手軽な「社会人の学び直し」手段といえます。
大学・専門学校のリカレント教育
体系的な知識や資格を得たいなら、大学・専門学校での学び直しもおすすめです。 夜間・通信制コースも多く、働きながら学ぶ社会人のサポート体制が整ってきています。
| 教育機関 | 特徴 | 取得できる資格・スキル |
|---|---|---|
| 大学 | オンライン・スクーリング | 専門知識・学士号 |
| 大学院 | 社会人入試・通信制 | 修士・博士号 |
| 専門学校 | 短期・資格特化 | 国家資格・実践スキル |
例えば放送大学では、BSテレビ・ラジオ、インターネットによる放送授業や実際の教室で学ぶ面接授業、オンライン授業やZoomを活用したライブWeb授業など、多様な授業スタイルを展開しています。
次項で紹介する文部科学省・厚生労働省の補助制度(給付金・奨学金)を利用すれば、経済的負担を軽減して学べます。
リカレント教育を支援する制度と事業 ―国・自治体・企業のサポートを活用しよう
リカレント教育を推進するために、国や自治体では多様な支援制度を整備しています。 代表的な支援内容を以下にまとめます。
| 制度の種類 | 概要 | 提供機関 |
|---|---|---|
| 教育訓練給付金 | 学費の一部または全額を補助 | 厚生労働省(ハローワーク) |
| 奨学金支援制度(貸与型) | 第一種奨学金(利息あり)と第二種奨学金(利息なし)の2種類 | 日本学生支援機構 |
| 無料・低価格講座(オンライン・対面) | 国や自治体が提供する講座 | 文部科学省、経済産業省、地方自治体 |
| 職業訓練・リスキリング | 専門スキル習得を目的とした研修 | 厚生労働省(ハローワーク、公共職業訓練校) |
| 相談窓口・情報提供 | 学び直しの相談・サポート | 厚生労働省委託事業者、教育機関、公的支援センター |
最新情報は厚生労働省・文部科学省の公式サイトで確認しましょう。 これらの制度を活用すれば、費用・時間のハードルを下げて学び直しが可能です。
企業内研修とその活用
勤務先の企業内研修も学び直しの一環です。企業は人材育成を目的に、スキルアップ研修・管理職研修・リスキリング研修などを実施しています。
- 業務効率化・DX推進を目的としたリスキリング研修
- 管理職・リーダー育成プログラム
- ビジネスマナー・IT研修などの基礎研修
学んだ内容を実務に活かすことで、キャリア形成と企業成長の双方に貢献できます。
学び直しを成功させる時間管理術 ―忙しい社会人でも続けられるコツ
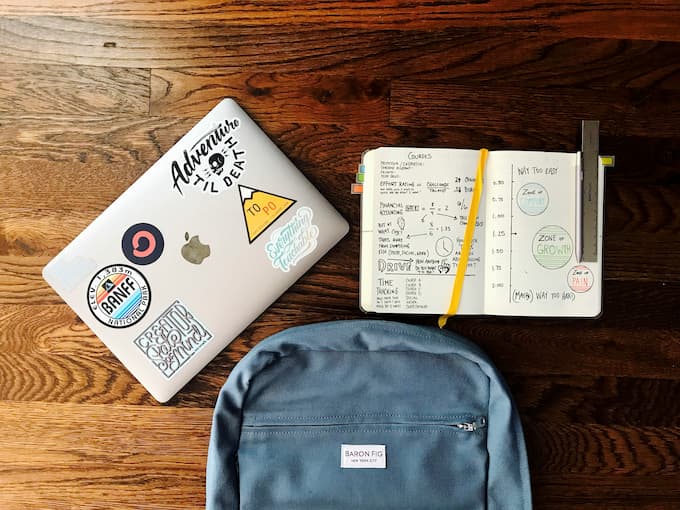
社会人が学び直しをする上での最大の課題は「時間の確保」です。 以下のポイントを意識することで、無理なく学びを続けられます。
| ポイント | 具体策 |
|---|---|
| 優先順位の明確化 | 重要タスクと学習時間をスケジュール化 |
| 隙間時間の活用 | 通勤・休憩・夜の30分を有効活用 |
| 短期目標の設定 | 1週間ごとの達成目標を立てる |
| デジタルツール活用 | GoogleカレンダーやTodoアプリで可視化 |
特に「短時間集中×継続」がカギ。15〜30分でも毎日積み上げることで大きな成果につながります。
>関連記事:社会人のスキルアップ戦略|キャリアを伸ばす実践方法と成功の秘訣
まとめ:学び直しは「キャリアを再設計する力」
社会人の学び直しは、単なるスキルアップではなく、自分のキャリアを再構築し、生涯のリスキリングや資格取得に繋げるチャンスです。リカレント教育を通じて、新しいスキルや知識を身につけることで、これからの仕事や人生における可能性を大きく広げることができます。
時間や費用の制約を感じることもあるでしょうが、オンライン講座や給付金制度、厚生労働省の推進するマナパス支援や無料相談サービスなど、多様なサポートが用意されています。まずは自分らしい学び方を見つけ、少しずつでも行動に移してみましょう。
学び直しは一歩踏み出す勇気さえあれば、誰にでも実現可能です。あなたのキャリアをより豊かにするための第一歩を、今日から始めてみましょう。

この記事を書いた人:パソコン市民講座編集部
リクルート、出版社、テレビ通販、ECなど複数業界で「伝える」「売る」「育てる」の現場を横断してきた実践派マーケター。現在は教育系企業でビジネスDX・SNSマーケ・EC講座などを設計し、受講からキャリア支援まで一気通貫で支援する構造設計を担う。 コンテンツ制作から広告運用、LP・CRM設計、SNS戦略、MA活用、商品開発、社外提携まで、ひとつの講座を“仕組みごと”作るプロフェッショナル。